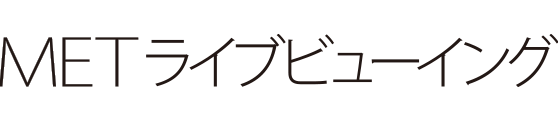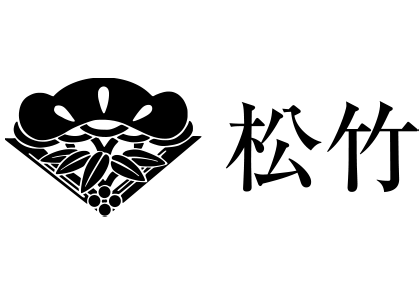《ヴォツェック》みどころレポート
音楽評論 東条碩夫
 今作の最大の主人公は、ヴォツェックでもなく、マリーでもなく、むしろ現代の荒廃した混乱の世界を描くウィリアム・ケントリッジの舞台映像かもしれない。
今作の最大の主人公は、ヴォツェックでもなく、マリーでもなく、むしろ現代の荒廃した混乱の世界を描くウィリアム・ケントリッジの舞台映像かもしれない。
ドローイング・アニメの巨匠として有名な彼のMETにおける演出は、ショスタコーヴィチの《鼻》とベルクの《ルル》に続く、これが3作目である。
そしてその映像アイディアは、いよいよ精密化し、多様さを加えている。つまり、どこまでが舞台装置で、どこからが映像で、しかもどれが人物だか、それさえ判らなくさせるほどの精妙さなのだ。
 この舞台は、全てが「混沌」の中にある。舞台美術(ザビーネ・トゥニセン)は、この劇場の舞台いっぱいに、雑多な光景を展開する。さながら荒廃した世界か、廃墟かといったところだ。この映像演出は舞台全体を観ることを主眼としているので、その意味でもカメラが個々の歌手のアップよりも、舞台全景を多くとらえているのは賢明な手法である。
この舞台は、全てが「混沌」の中にある。舞台美術(ザビーネ・トゥニセン)は、この劇場の舞台いっぱいに、雑多な光景を展開する。さながら荒廃した世界か、廃墟かといったところだ。この映像演出は舞台全体を観ることを主眼としているので、その意味でもカメラが個々の歌手のアップよりも、舞台全景を多くとらえているのは賢明な手法である。
たとえば兵舎の中で、貧しい哀れなヴォツェックが上官からさんざんに侮辱される場面、あるいは彼の妻マリーが自己の不倫を悔いて祈る場面━━いずれも舞台全体の光景は混沌たる映像に満たされる。それらは、彼らの精神のどうしようもない荒廃、そして彼らを取り巻く社会の荒廃を象徴しているものにほかならない。
その光景は、言葉に言い表せないほど凄まじい。かつてこれほど、主人公たちの内面を具象化した舞台の《ヴォツェック》があったろうか?
 登場人物は、その混沌の中からいつの間にか現われる。そしてまたその混沌の闇の中へ、じりじりと溶け込んで行く。マリーは倒れたまま群衆の中に埋もれ、廃墟と同化してしまう。「池の中へ去る」ヴォツェックも同様、その姿はすっと背景の廃墟と一体化するように消えてしまい、彼がこの世に存在したという痕跡すら定かでなくなるのだ。ドラマの冒頭で彼が口走っていたように、それが底辺に生きる人間の宿命なのか。何という無常!
登場人物は、その混沌の中からいつの間にか現われる。そしてまたその混沌の闇の中へ、じりじりと溶け込んで行く。マリーは倒れたまま群衆の中に埋もれ、廃墟と同化してしまう。「池の中へ去る」ヴォツェックも同様、その姿はすっと背景の廃墟と一体化するように消えてしまい、彼がこの世に存在したという痕跡すら定かでなくなるのだ。ドラマの冒頭で彼が口走っていたように、それが底辺に生きる人間の宿命なのか。何という無常!
マリーの子供が身体を侵されており、それは病院の看護師に介抱されている人形で表現される、というのもショッキングな光景だ。
ケントリッジのアイディアは、今作で、社会派的な方向へまた大きな一歩を踏み出したようである。
 だが、こう書いて来ると、なんだかとても恐ろしいオペラのように思われそうだが、実はそんなことはないのである。
だが、こう書いて来ると、なんだかとても恐ろしいオペラのように思われそうだが、実はそんなことはないのである。
まず音楽が素晴らしい。MET音楽監督ヤニック・ネゼ=セガンの指揮は、ドイツ・オペラの世界でも繊細さをも備えた叙情的な美しさを備えて見事だ。今や彼の実力は全開であろう。
クライマックスの悲劇の場面での演奏でも、「真の恐怖はあとから襲い掛かって来る」と言われる有名な全管弦楽の猛烈なクレッシェンドは、凄まじい。各場面転換の音楽も、細やかな画像の動きによってさらに緊張感を強められている。
とにかく、これは凄まじい《ヴォツェック》だ。必聴、必見と申し上げたい。
休憩はない。