お知らせ
HOME > お知らせ > ○てらやん日記● 課外授業 鳴物ワークショップ
○てらやん日記● 課外授業 鳴物ワークショップ
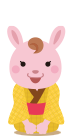
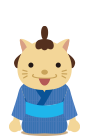
こんにちは!てら子とやー坊です。
今回わたしがレポートするのは、「鳴物ワークショップ」です。
「鳴物」とは、歌舞伎のお話に音を付ける「囃子方」さんが使う楽器や演奏のことです。
太鼓や鼓、竹笛など、三味線以外の楽器を使います。舞台下手の「黒御簾」で演奏されることが多いです。
今回は、寺子屋音楽部門(鳴物)統括講師である、田中傳左衛門先生と社中の皆さんに鳴物のことを教えて頂きました。
基礎コース・発展コースそれぞれ違う内容のワークショップが行われ、盛りだくさんのワークショップでした!わたしたちふたりで、当日の様子をお知らせします!

まずは、基礎コースのおともだち向けのワークショップです。
基礎コースのワークショップでは、「一番太鼓」の叩き方を学びました。
班ごとに分かれて、「どん・どん・どんとこい」の調子に合わせて楽太鼓の叩き方を直接教えていただきました。
楽太鼓は、小さなおともだちの背と変わらない大きさです。
太鼓の音がからだに響いて、ものすごい迫力でした!!
最後は班ごとに発表。短い時間で集中して一所懸命お稽古した成果を発表しました。


 次にレポートするのは発展コースのおともだち向けのワークショップ。
次にレポートするのは発展コースのおともだち向けのワークショップ。
「おはなしに音をつけよう」プログラム企画:KAAT神奈川芸術劇場

KAAT神奈川芸術劇場さんが以前より行っているプログラム「おはなしに音をつけよう」が寺子屋生徒向けに開催されました。
「囃子方」のお仕事である、お話に音をつける、ということはどういうことなのかを知るために、昔話や童話を題材に、物語の内容に合わせて情景などを想像し、楽器を使い自由に作調してみよう、という趣旨のプログラムです。
今回の寺子屋生向けのワークショップの題材は、昔話『三枚のお札』。
『三枚のお札』は、お寺の小僧さんが和尚さんの注意を聞かずに山に栗拾いに出かけてしまい、山で山姥に出会ってしまう。三枚のお札を使い山や川を出しながら、必死の思いで山姥から逃げていく…という、スペクタクルなお話です。
班ごとに分かれ、このお話に音をつけていきます。
栗がカラカラと落ちる音は、どんな楽器をつかおうか?この台詞のあとは、どんな音が合うかな?と先生を中心に話し合って、決めていくおともだち。
みんな、お話に入り込んで想像します。


最後には、新派の女優さんである磨貴こずえさんの朗読に合わせ、保護者の前で班ごとに発表しました。

最後には、傳左衛門先生から、「普段、文章を読んでいて音を想像するということは少なかったかもしれません。ひとつの文章を読んで、さまざまな想像をしていく頭を持つことはとても大事なこと。台詞を読むにしても、ただきれいに文章を読むだけではだめで、気持ちを想像して心を込めることが大事。これから、そんなことを意識しながらやっていくと多くのことを想像し、考えられるようになると思います。」と激励をいただきました。
とても充実したプログラムのワークショップ、おともだちは「楽しかった~!」と多くを学んだ様子で帰っていきました。
田中傳左衛門先生、社中の皆さん、磨貴こずえさん、KAATの皆さん、本当にありがとうございました!!
寺子屋お知らせメールサービス
HPの「お知らせ」を更新した際にメールでお知らせします。
terakoya@shochiku.co.jpまで
お名前と「メールでのお知らせ希望」と記載の上、ご送信ください。
記事検索