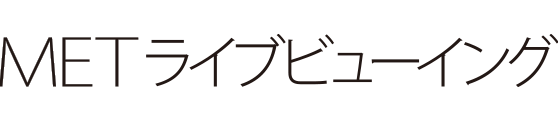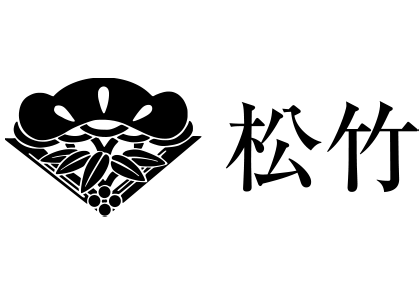R・シュトラウス《アラベッラ》みどころレポート
青山学院大学教授/日本リヒャルト・シュトラウス協会事務局長 広瀬大介
 1929年、70歳代にさしかかろうかというリヒャルト・シュトラウスは、およそ20年以上にわたって苦楽をともにしてきたオペラ制作のパートナー、フーゴー・フォン・ホフマンスタールを突然喪います。ホフマンスタールが遺した《アラベッラ》の台本は、シュトラウスとのやりとりによって第1幕は完璧な出来映えとなっていましたが、第2幕、第3幕はほぼ草稿のまま。それでも、シュトラウスは仕事仲間にして友であった故人の想い出をかたちにすべく、作曲を進めたのです(初演:1933年)。
1929年、70歳代にさしかかろうかというリヒャルト・シュトラウスは、およそ20年以上にわたって苦楽をともにしてきたオペラ制作のパートナー、フーゴー・フォン・ホフマンスタールを突然喪います。ホフマンスタールが遺した《アラベッラ》の台本は、シュトラウスとのやりとりによって第1幕は完璧な出来映えとなっていましたが、第2幕、第3幕はほぼ草稿のまま。それでも、シュトラウスは仕事仲間にして友であった故人の想い出をかたちにすべく、作曲を進めたのです(初演:1933年)。
 時代こそ違え、ウィーンの上流階級社会を描いているという点で、本作は早くから《ばらの騎士》と比較され続けてきました。とはいえ、タイトルロールであるヒロイン、アラベッラの「受け身」な性格は、積極的な《ばらの騎士》の登場人物たちに比べれば確かに影が薄くみえてしまい、しばしば作品の受容において誤解され続けてきたように思います。自分にはきっと「ふさわしい殿方 Der Richtige」があらわれるに違いない、という強い確信、そしてスラヴォニア(クロアチア東部)からやって来た大富豪マンドリカを見かけてこのひとこそ「ふさわしい」と感じられる天性の勘を持ち合わせています。自分の容姿だけを褒め称えて求婚する貴族たちとは異なり、生きることに貪欲な、ポジティヴな力強さをマンドリカに見出したのでしょうが、主体的に生きる自由をもった現代人から見れば、アラベッラのどこか消極的な人生観に共感しづらいのはしかたのないところでしょう。
時代こそ違え、ウィーンの上流階級社会を描いているという点で、本作は早くから《ばらの騎士》と比較され続けてきました。とはいえ、タイトルロールであるヒロイン、アラベッラの「受け身」な性格は、積極的な《ばらの騎士》の登場人物たちに比べれば確かに影が薄くみえてしまい、しばしば作品の受容において誤解され続けてきたように思います。自分にはきっと「ふさわしい殿方 Der Richtige」があらわれるに違いない、という強い確信、そしてスラヴォニア(クロアチア東部)からやって来た大富豪マンドリカを見かけてこのひとこそ「ふさわしい」と感じられる天性の勘を持ち合わせています。自分の容姿だけを褒め称えて求婚する貴族たちとは異なり、生きることに貪欲な、ポジティヴな力強さをマンドリカに見出したのでしょうが、主体的に生きる自由をもった現代人から見れば、アラベッラのどこか消極的な人生観に共感しづらいのはしかたのないところでしょう。
 この違和感は、ギャンブルで身を持ち崩した父のせいで破産寸前となった家族において、男装のまま生きることを強いられたアラベッラの妹、ズデンカの存在によって、ようやく納得ゆくものとなります。アラベッラも、ズデンカも、自身の生き方を主体的に選べないという点において変わりはありません。アラベッラが「ふさわしい殿方」にめぐり会えるまでは、と結婚を渋るのは、金持ちと結ばれることで家族を救ってほしい、という、自身を財産の「かた」と見做す両親の身勝手な願望に対する、消極的な抵抗でもあったはずです。
この違和感は、ギャンブルで身を持ち崩した父のせいで破産寸前となった家族において、男装のまま生きることを強いられたアラベッラの妹、ズデンカの存在によって、ようやく納得ゆくものとなります。アラベッラも、ズデンカも、自身の生き方を主体的に選べないという点において変わりはありません。アラベッラが「ふさわしい殿方」にめぐり会えるまでは、と結婚を渋るのは、金持ちと結ばれることで家族を救ってほしい、という、自身を財産の「かた」と見做す両親の身勝手な願望に対する、消極的な抵抗でもあったはずです。
 ズデンカは、姉に幸せになってほしい、そしてその姉を愛してやまない(財産を持たぬが故にアラベッラとは結ばれようもない)軍人マッテオの苦悩を救うため、自分がアラベッラの身代わりとなってマッテオにその身を捧げる、という(これは現代人から見てもかなり思い切った)決断を下し、実行に移します。ズデンカは、他者の幸せを願い、そのために自身を犠牲にすることで、この物語の登場人物全員を救いました。妹の自己犠牲に心動かされたアラベッラは、幕切れで一杯の水を(マンドリカの故郷の風習に従って)未来の夫に与え、自身の夫をみずからの意志で選びます。アラベッラは主体的になにかを掴み取る、という決断を人生で初めてくだし、最後の最後でその人間的成長を印象づけるのです。
ズデンカは、姉に幸せになってほしい、そしてその姉を愛してやまない(財産を持たぬが故にアラベッラとは結ばれようもない)軍人マッテオの苦悩を救うため、自分がアラベッラの身代わりとなってマッテオにその身を捧げる、という(これは現代人から見てもかなり思い切った)決断を下し、実行に移します。ズデンカは、他者の幸せを願い、そのために自身を犠牲にすることで、この物語の登場人物全員を救いました。妹の自己犠牲に心動かされたアラベッラは、幕切れで一杯の水を(マンドリカの故郷の風習に従って)未来の夫に与え、自身の夫をみずからの意志で選びます。アラベッラは主体的になにかを掴み取る、という決断を人生で初めてくだし、最後の最後でその人間的成長を印象づけるのです。