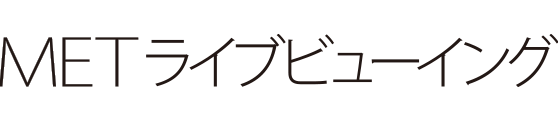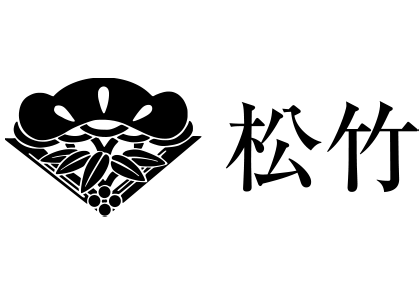《フィガロの結婚》みどころレポート
音楽評論家 奥田佳道
 観てよし、聴いてよし、観終わってまたよし。
観てよし、聴いてよし、観終わってまたよし。
色とりどりの音楽が小気味よくスピーディに駆け巡るかと思えば、しっとりとした味わいにも事欠かない《フィガロの結婚》を愛してやまないファンも、オペラはこれからという方も、これは必見・必聴の舞台だ。
イギリスの至宝ともいうべき演出家リチャード・エアが創った、クラシカルかつ奥行きのある舞台に、胸ときめく。
今をときめく歌い手たちは立ち居振る舞いからして美しい。魅せる。思わずほほ緩む面もたくさん。しかも、いついかなる場面でも、長調と短調の領域を自在に行き来するモーツァルトの音楽と、しなやかに呼応。このオペラの生命線でもあるアンサンブル(重唱)が、また素晴らしい。みな、表情豊かに舞台を縦横に泳ぐ。
 フィガロ役は今この人ともいえるマイケル・スムエル、スザンナ役はMETではムゼッタ役(ラ・ボエーム)も歌ったオルガ・クルチンスカ、伯爵役にアメリカ・カナダのオペラシーンに欠かせないジョシュア・ホプキンス、伯爵夫人役を抜群のステージプレゼンスを誇るプリマドンナ、フェデリカ・ロンバルディ。ケルビーノ役にはバロックとコンテンポラリーという二極を行き来するサン=リー・ピアース。皆主役で、惚れ惚れするばかりの歌役者たちだ。
フィガロ役は今この人ともいえるマイケル・スムエル、スザンナ役はMETではムゼッタ役(ラ・ボエーム)も歌ったオルガ・クルチンスカ、伯爵役にアメリカ・カナダのオペラシーンに欠かせないジョシュア・ホプキンス、伯爵夫人役を抜群のステージプレゼンスを誇るプリマドンナ、フェデリカ・ロンバルディ。ケルビーノ役にはバロックとコンテンポラリーという二極を行き来するサン=リー・ピアース。皆主役で、惚れ惚れするばかりの歌役者たちだ。
駆け引きや逢引の場面も注目のシーンである《フィガロの結婚》だが、二組の結婚式が教えてくれるように、オペラの主題は愛、人間賛歌で、amor(アモール、愛)、dolce(ドルチェ、甘く優しく),pace(パーチェ、平和)という言葉が美しく響く。
最後、伯爵が伯爵夫人に許しをこう場面で繰り返される言葉はperdono(ペルドーノ、許しておくれ)である。いろいろあった二人──強さも弱さも見せる伯爵ジョシュア・ホプキンスと、美貌の伯爵夫人フェデリカ・ロンバルディ――が織り成す、大人のドラマに喝采を。

フランスの劇作家ボーマルシェの戯曲「狂騒の一日あるいはフィガロの結婚」をベースに、モーツァルトとウィーンの宮廷詩人ダ・ポンテ(台本)という、舞台史上最強コンビが創り上げた《フィガロの結婚》。それはあの心躍るニ長調の序曲で始まり、「さあ花火を打ち上げて、愉しいマーチの調べにあわせて、皆でお祝いにいきましょう」という喜ばしいニ長調で幕となる。五線譜に#記号ふたつのニ長調は、モーツァルトの時代、祝祭の調べにして、愛、神に感謝する調べでもあった。
モーツァルトの音楽も歌い手の歌も動きのある舞台も生彩に富んだMET最新の《フィガロの結婚》は、聴き手のオペラデビューにも相応しい。ぜひ。